| 大和高田・ものづくり歴史背景 | ||
先史古代 中世・江戸前期 中世・江戸前期 江戸時代 江戸時代 明治初期 明治初期 明治中期〜大正期 明治中期〜大正期 昭和初期〜現代 昭和初期〜現代 明治〜現代 明治〜現代
| ||
| さまざまな"近代ものづくり集団"の出現 | ||
| 明治開国来の衝撃で主力の大和木綿・大和絣が衰退しましたが織物や近代紡績に活路を見出すと共に、この地の先人は蓄積した技術と大都市・大阪と密着しての連携事業、また先進国の技術導入もはかり屈することなく「繊維・農工機械」「鋳物」(五位堂)「金属製品」などのものづくりを起業化し幾多の経済危機を乗り越えてきました。
とりわけ明治中期の洋風化に対応し「メリヤス・産業」の導入、全国屈指の「靴下産業」の勃興(ぼっこう)。大正3年(1914年)には「生ゴム靴生産」(松塚)大和絣以来の「染色業」(奥田)大正末に割烹着に始まる「縫製業」、大正6年(1917年)に「貝ボタン工業」、皮革伝統技術の上に「軍靴・背嚢(はいのう)・膠(にかわ)」「酒造」など多種の「ものづくり」が起こります。 こうした伝統が時代の変化に対応しつつ今なお健在であります。 それらは現在の「靴下」、「ニット」、「プラスチック製品」「工業用手袋安全保護具」「産業・工作機械」「サンダル」「機械金属」「衣料縫製品」「染色」「たたみ」「機械部材」等に引き継がれています。平成19年11月にものづくりの再興を期して始まった「大和高田ものづくりメッセ」には35企業が参加出展。これらの企業を軸に異業種交流も始まり、今新たな挑戦が始まろうとしています。 これこそ古くからの当地の「ものづくり集団の底力」と言えましょう。 | ||
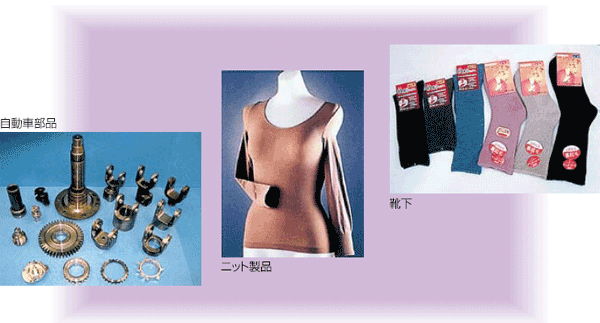 | ||
このページは平成19年度小規模事業者全国展開支援事業 大和高田商工会議所 にぎわい大和高田 発行の冊子より転載しました。 | ||